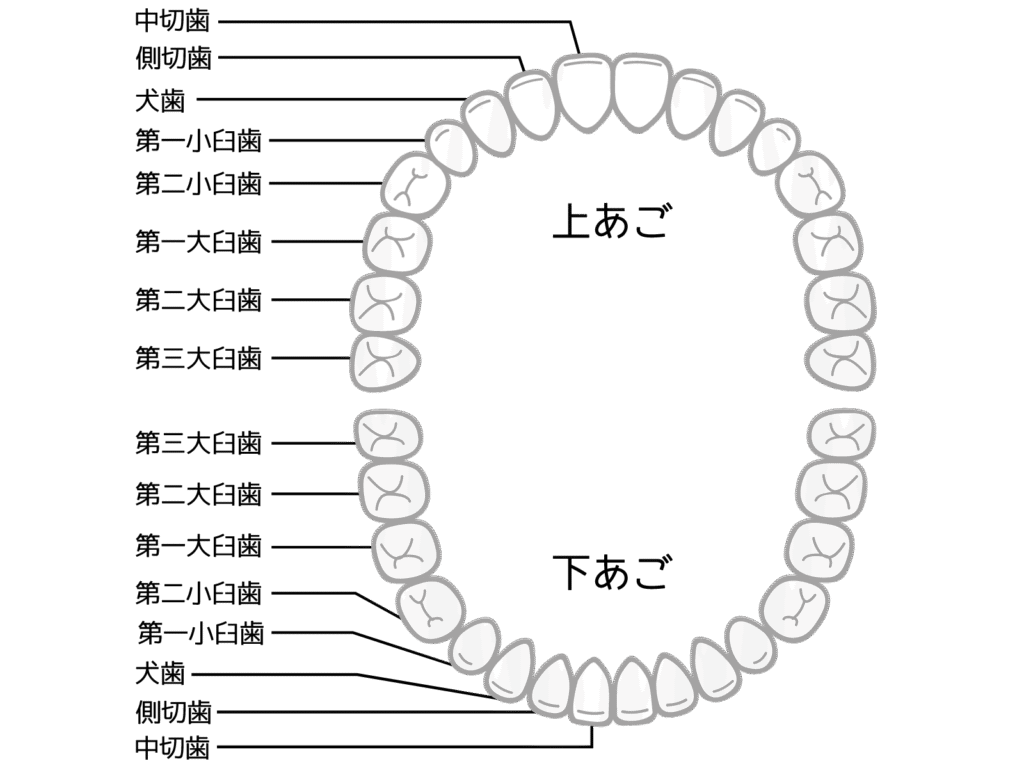みなさん、こんにちは。伊藤歯科医院です。
みなさんが当たり前のように「親知らず」と呼んでいる第三大臼歯ですが、なぜ「親知らず」という名前になってのでしょうか?
この名前がついた由来は、「親が知らないうちに生えてくる歯」=「親知らず」と言われています。
通常の永久歯は10代で生えそろいますが、親知らずは17~30歳ごろに生えてくることが多く、その頃には親元を離れている人も多かったため、このように呼ばれるようになったようです。
では、海外でも親知らずのように、特別な名前がついているのでしょうか?
英語圏:「Wisdom Tooth(知恵の歯)」
アメリカやイギリスでは、「Wisdom Tooth(ウィズダム・トゥース)」と呼ばれています。
これは、知恵がつく年頃(17~25歳ごろ)に生えることから名付けられました。
「親」ではなく「精神的な成長」に注目しているところが面白いですね。
フランス語:「Dent de sagesse(知恵の歯)」
フランス語でも「sagesse=知恵」の歯。
やはり「成熟する頃に生える歯」としてとらえられています。
ドイツ語:「Weisheitszahn(知恵の歯)」
ドイツ語も同じく「知恵の歯」。
“歯”に“人生経験”や“分別”が関係していると考えるのは、ヨーロッパ圏で共通のようです。
イタリア語:「Dente del giudizio(判断の歯)」
イタリア語では「判断の歯」と呼ばれています。
「冷静な判断ができる年齢になってから生える歯」という意味が込められていて、哲学的な響きも感じられます。
スペイン語:「Muelas del juicio(判断の歯)」
イタリアと同じく「判断」や「理性」にちなんだ呼び名です。
言語は違っても、“大人になる時期に生える特別な歯”という感覚は似ているようです。
韓国語:「사랑니(サランニ)=愛の歯」
韓国ではなんと「愛の歯」と呼ばれています!
恋をする頃に生える歯という意味で、ちょっとロマンチックな印象ですね。
同じ「親知らず」でも、日本は”親子の関係に”に注目、欧米では”知恵・判断・愛”など、精神的な成長に焦点が当てられているようです。
どの国でも「人生の節目」感じていることが分かりますね。
そもそも、親知らずが「生えてこない人」や「もともと存在しない人」もいます。
気になる方は、レントゲンを撮ればすぐに確認できますので、お気軽にご相談ください😊